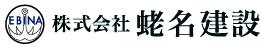型枠工事いろは
COLUMN
上層階のスラブや梁を積み上げていくときの支保工
支保工は、スラブや梁を下からささえる支柱の工事です。スラブや梁のコンクリートが固まったら取り外されますが、完全に固まる前に上層階の工事が始まります。そこで、支柱はそのままに上層階を工事します。
このコラムを読む >
生コン会社から現場までの生コン輸送時間とは?
生コン会社で練り混ぜされたコンクリートは、すぐに塊始めます。そこでミキサー車で拡販しながら工事現場まで運び、生コンの打ち込みまでの時間は、外気温が25℃以下なら120分以内、25℃以上なら90分以内に行われます。
このコラムを読む >
ポルトランドセメントとは?
一般的なセメントはポルトランドセメントが正式名称です。ポルトランドの由来は、イギリスのポートランド島にある石灰石の色と似ていることから、そのように命名されたそうです。レンガ職人のジョセフ・アスプディンが、その名称で特許を取り、その名称が今も残っています。
このコラムを読む >
スライディングフォームとは?
スライディングフォーム工法とは、継目のない高い壁をつくりたい場合、コンクリートが固まったら型枠を上側にスライドさせていって、その上からコンクリートを流し込んでいく工法です。
このコラムを読む >
ハーフプレキャストとは?
ハーフプレキャスト(ハーフPC)とは、鉄筋コンクリートの壁やスラブなどを工場で製造しておき、工事現場に運び込んで組み立てて建物を建設していく工法のことです。プレハブのように建物を組み立てていくことができます。
このコラムを読む >
型枠工事の道具
型枠工事で使用する道具は、普段持ち歩いている道具は人や作業内容によって異なりますが、基本的にはハンマー、セパレータフック、ラチェットレンチ、バール、ペンチ、メジャー、墨つぼです。
このコラムを読む >
型枠工事の仕事内容
型枠工事の仕事内容は、型枠の加工、現場への型枠の搬入、型枠の組立や取り付け、固定、コンクリートが固まったら型枠の取り外しと搬出、洗浄などを行います。現場によっては、フォークリフトやクレーンの運転も行います。
このコラムを読む >
スラブ用型枠のトラス鋼製仮設梁
トラス鋼製仮設梁とは、鋼棒を三角の形状にくみ上げて、両端のみで支えることができる強度のある支保工です。通常は使用しませんが、スラブの型枠工事で使用される場合があります。
このコラムを読む >
鉄筋コンクリートのかぶり厚さとは?
かぶり厚さとは、鉄筋コンクリートの中に入っている鉄筋から外までのコンクリートの厚さのことです。かぶり厚さがないと、コンクリートのひび割れで鉄筋が腐食してしまい、鉄筋コンクリートが劣化しやすくなります。
このコラムを読む >
コンクリートのジャンカとは?
コンクリートを打設して固まり、型枠を外したときに、コンクリートの表演がなべらかでなく、凸凹してザラザラしてしまうことがあります。このような状態のことを、「ジャンカ」といいます。
このコラムを読む >
型枠工事の建入れ直しとは?
建入れ直しとは、建物の柱や梁などの構造物の精度を高めるために、型枠の位置を調整する作業のことです。型枠を鎖でつないで、ターンバックルを調整して、型枠の精度を高めます。
このコラムを読む >
型枠工事の根がらみとは?
パイプサポートでは届かない高さの場所のスラブや梁などの型枠工事では、鋼管枠を支柱とすることがあります。その足元の滑動を防ぐために、鋼管枠の足元にパイプを横に這わせて固定しますが、この固定する方法のことを「根がらみ」と言います。
このコラムを読む >
型枠工事のクランプとは?
型枠工事では、クランプという金具をたくさん使用します。クランプとは、日本語では「留め金」と訳されるものと思われます。型枠工事では、主にパイプを固定するものをクランプと呼んでいます。
このコラムを読む >
鋼管枠を用いた型枠支保工とは?
鋼管枠とは、現場の足場として用いられている門型の支柱のことです。これを、型枠支保工として用いる型枠工事があります。天上の高い場所のスラブに用いられる型枠で使用されます。このような支保工のことを、「枠組支保工」と言います。
このコラムを読む >
パイプサポートの水平つなぎとは?
パイプサポートは、高さが3.5mを超える場合には、高さ2m以内で水平つなぎを設置します。水平つなぎとは、パイプサポート同士を棒でつなぎ合わせる部材のことです。パイプサポートと水平つなぎは、緊結金具で固定します。
このコラムを読む >
パイプサポートの継ぎ足し
スラブや梁の高さが高くて、パイプサポート1本では長さが足りない場合、パイプサポートを2本まで継ぎ足すことができます。接合部は、4本のボルトか、専用金具で固定します。
このコラムを読む >
型枠工事の端太材とは?
端太材の読み方は、「ばたざい」です。端太材とは、型枠工事で用いられる補強用の角材やパイプのことです。材質には、木製、鋼製の端太材があります。木製角材のことを端太角(ばたかく)と言われることもあります。
このコラムを読む >
- 次のページ >